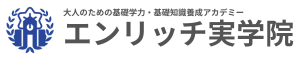おすすめ書籍
読書📚️
読書は知識・思考力を身につけるための基本中の基本です。
古今東西でも影響力を持っている人・歴史に名を残した人というのは、ほぼ例外なく読書習慣があります。
そしてエンリッチ実学院のゴールの1つは、
- 『正しい本の読み方』
- 『知の巨人が選んだ世界の名著200』
- 『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』
などの書籍で紹介されているような、「読書」という世界において最高峰の本をゆっくりとでも、しっかり理解して読めるようになること。
ここまでできれば、”基礎”は十分に身についていると言っていいと思います。
『読書の技法』(佐藤優 著)
エンリッチ実学院を立ち上げるきっかけにもなった本。
著者の佐藤優さんは「知の巨人」とも言われ、元々は対ロシア外交の最前線で活躍されていた、いわば”知識”を扱うプロです。
そんな佐藤優さんがこの本では「"本物"の知識・思考力を身につけるには、高校・大学入試レベルの基礎学力・基礎知識をしっかり身につけることが大切である」ということを繰り返し述べられ、佐藤さん自身、現在でも高校範囲の国語や数学・歴史・政治・経済を復習されているそうです。
こと”頭を使う”ことにおいて、基礎学力・基礎知識がいかに重要かが分かります。
詳細はこちら『正しい本の読み方』(橋爪大三郎 著)
社会学者の橋爪大三郎さんが書いた本。
この本の中間あたりにある「必ず読むべき大著者100人リスト」では、『聖書』『コーラン』『ブッダの真理のことば・感興のことば』など、歴史上でも極めて重要な書籍が紹介されています。
詳細はこちら国語力・読解力📖
国語力・読解力はありとあらゆる学問の中で基礎中の基礎中の基礎だと断言できます。
なぜなら、数学を勉強するにしても、英語・世界史・日本史・政治・経済など他の科目を勉強するにしても、この国語力・読解力がなければ理解できなかったり、浅い理解で終わってしまったりするからです。
さらに日々の読書においても、ちゃんと読んでいると思っても実は自分が読みたいように読んでいるだけだったり、読める本の幅が極端に狭くなってしまったりなど、国語力・読解力がなければ致命傷になります。
基礎学問・リベラルアーツを学ぶ上では、最初にこの国語力・読解力をマスターしてしまうことが極めて重要です。
『大学入試受かる漢字・用語パピルス1467』(出口汪 著)
「抽象」「還元」「普遍」など、現代文の文章、さらに一般書でも少し専門的な本になってくると、普段の会話では使用しないような単語がバンバン出てきます。
こうなってくると、今読んでいるのは日本語の文章だったとしても、それは英語を読んでいるのとほとんど変わらず、こういった漢字・用語を知らなければ”チンプンカンプン”になってしまいます。
この『大学入試受かる漢字・用語パピルス1467』は、そういった文章を読む上で重要な漢字・用語が、簡潔な解説とともにギュッと凝縮された問題集になります。
まずはこういった文章表現に特有の漢字・用語を覚えることで、文章を読むための基礎中の基礎の力を養います。
詳細はこちら『田村のやさしく語る現代文』(田村秀行 著)
「論理とはなにか」「読解力とはなにか」。
特に、学生時代に国語が苦手だった方にとっては、それは得体の知れないもののようにも思えると思います。
僕もその一人でしたが、腑に落れば意外とシンプルですし、さらに、論理的思考力・読解力というのは一生使えるスキルにもなります。
この『田村のやさしく語る現代文』はとても薄い参考書ですが、「論理とはなにか」「読解力とはなにか」ということが明確に、シンプルに解説されています。
解説と合わせて、この参考書に掲載されている問題を田村さんの解説で紐解いていくことで、掴みどころの分かりづらい「論理」「読解力」の基礎を身につけることができます。
詳細はこちら『Z会 現代文キーワード読解』(Z会編集部 著)
国語の問題を解く・文章を読む上では「背景知識」も非常に重要になってきます。
例えば、「近代化への反省として文化相対主義が生まれた」という文章を理解するためには、
- 「近代化」とは何か
- 「文化相対主義」とは何か
- 「合理主義」とは何か
といった知識が必要になってきます。
この『現代文キーワード読解』では、現代文の問題や一般書を読み解く上で重要な、そういった背景知識が丁寧に解説されており、この本を読むことで文章の読解はグッとしやすくなってきます。
詳細はこちら『共通テスト過去問研究 国語』(教学社編集部 編集)
昔は「共通一次」「センター試験」ともいわれた大学入試の関門試験。
毎年、50万人近くの受験者がいることもあり、出題される問題もとてもよく練られた良問揃いです。
そういった国語の良問をたくさん解いていくことによって、論理的思考力・読解力を強化してくことができます。
ちなみに解くのは大問1(評論文)・大問2(小説)だけでよく、大問3(古文)・大問4(漢文)は無視してかまいません。
詳細はこちら数学📐
数学力は簡単にいうと、「問題を無駄なく、最短距離で解決する力」、さらに「問題自体を正確に発見・定義する力」を養うことができます。
具体的には、
- 論理的思考力
- 批判的思考力(クリティカル・シンキング)
- 発想力(クリエイティビティ)
- 抽象的思考力
- 具体的思考力
- 仮説思考力
などの脳力を、問題演習を通して一気に鍛えることができます。
これらの脳力はいうまでもなく、仕事やビジネスでも非常に役に立ってくるスキルになります。
☆期間限定100円で提供中!エンリッチ実学院の「数学教室」について詳しくはこちら
『東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』(西成活裕 著)
数学に限らず、どんな学問でも最初に”全体像”を掴むことが非常に重要です。
全体像を先に掴んでしまえば、その学問がだいたいどういったものなのか、どれぐらいの範囲を学習するのかを把握することができますし、知識を覚える時にも”全体”と関連させながら知識を深く覚えることが可能になるからです。
この『東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』は内容としては、中学数学を取り扱っていますが、これから数学を学ぶ方にとっては、数学の全体像を掴むのにうってつけの本になります。
詳細はこちら『東大の先生!文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください!』(西成活裕 著)
こちらは上の「東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!」の続編で、内容は「統計」「数列」「ベクトル」「微分・積分」などの高校数学を取り扱っています。
エンリッチ実学院で取り扱っているのは主に高校範囲の知識になるので、高校数学の全体像を掴むにはうってつけです。
詳細はこちら『チャート式基礎と演習数学(白チャート)』(チャート研究所 編集)
高校数学のチャート式には主に「白」「黄」「青」「赤」の4種類がありますが、白チャートはこの4種の中で一番基礎的な問題集になります。
チャート式は解説が丁寧で、問題のすぐ下に解答があるという非常に復習がしやすい体裁になっているので、数学が全く苦手!という方でも短期間に数学の基礎を固めることが可能です。
ちなみにこの白チャートは一番基礎レベルといっても、きちんとこなせば数検準1級、大学でいえばMARCH・関関同立レベルまでの数学力が身につきます。
詳細はこちら『合格!数学実力UP!問題集』(馬場 敬之 著)
上の白チャートをマスターしたあとにさらに数学力を伸ばしたい場合にオススメの問題集。
白チャートと同じく、こちらの問題集も解説が非常に丁寧で、問題のすぐ下に解答が載せてあり、とても復習がしやすい体裁になっています。
難易度でいえば「標準」レベルですが、この問題集までマスターすることで、日本の最難関大学である東大・京大の問題まで解けるようになります。
詳細はこちら『実戦 数学重要問題集』(数研出版編集部 編集)
上でご紹介した問題集の演習が基礎練習だとすれば、それらの知識を縦横無尽に使って実際に問題を解くのは実戦にあたります。
この実戦を通して、数学をより深く理解することができます。
この『実戦 数学重要問題集』では「場合の数・確率」「ベクトル」「極限」というように単元ごとにありとあらゆる大学の良問が集められている問題集になります。
問題数が豊富で、その豊富な実戦を積み重ねることによって、現実社会でも応用できるような数学的思考力を鍛えることが可能です。
詳細はこちら『東大・京大 25か年シリーズ』
上でご紹介した『合格!数学実力UP!問題集』レベルまで基礎を身につけることができれば、ぜひ解いていただきたいのが日本のトップ大学である東京大学・京都大学の問題。
東京大学・京都大学の問題は毎年、その他の各大学が研究して受験問題を作成していると言われるほどの良問揃いです。
問題のスタイルとしてはどちらの大学も知識”量”を問うよりはむしろ、知識としては基本的なことを聞きながらも、複数の単元を組み合わせた、かなり高度な”思考力”を問うてきます。
この『東大・京大 25か年シリーズ』では題名どおり、東大・京大の25年分の過去問題が単元ごとに整理・レベル分けされ、これら最高峰の問題をたくさん解いていくことにより、現代社会で極めて役に立つ数学的思考力を洗練させていくことが可能です。
詳細はこちら世界史・日本史🌍️
利害関係、各国の思惑、同盟、そして裏切り…。
歴史は人生の教科書といってもよく、また、現代社会でも極めて役に立つ戦略の宝庫でもあります。
下手に自己啓発書やビジネス書を数千冊など読むよりは、世界史・日本史に深く通ずる方が100倍役に立つと思います。
読書においても少し高度な書籍になると必ず歴史の知識が入ってきて、こういった歴史の知識がなければ読める本の幅は一気に狭くなってしまいます。
さらに現代社会でもパレスチナ問題、資本主義社会、共産主義思想など、全て過去からつながっているので、これらを読み解く上でも歴史の知識は必須になってきます。
『1分間世界史1200』(石井貴士 著)
学んだことがある方なら分かると思いますが、歴史は英語と同じく、単語・人物名・用語の意味が分からなければそもそも文章が全く理解できません。
この『1分間世界史1200』は世界史で頻出する最重要の単語・人物名・用語を1200個集めた単語集のようなもの。
朗読CDも発売されているので、iPhoneなどに音源を入れて毎日聞き流し、一問一答を繰り返すことで世界史の全体像を一気に把握でき、文章もスラスラ理解できるようになります。
詳細はこちら『30日完成 スピードマスター世界史問題集』(黒河潤二 編集)
高校レベルの世界史をマスターするための問題集。
おそらく世界史の問題集の中でも最も薄い問題集ですが、その分、無駄が省かれ、情報が凝縮されているので、最短距離で世界史をマスターすることが可能です。
この薄い問題集でも、マスターすれば共通テストで8割・9割は取れるレベルになりますし、普段の読書においてもかなり高度な本の論理展開でもついていくことが可能になります。
詳細はこちら『30日完成 スピードマスター日本史問題集』(東京都歴史教育研究会 編集)
上の『30日完成 スピードマスター世界史問題集』と同じく、高校レベルの日本史をマスターするための問題集。
こちらも情報がギュッと凝縮され、反復演習を重ねることで最短距離で日本史をマスターすることが可能です。
詳細はこちら